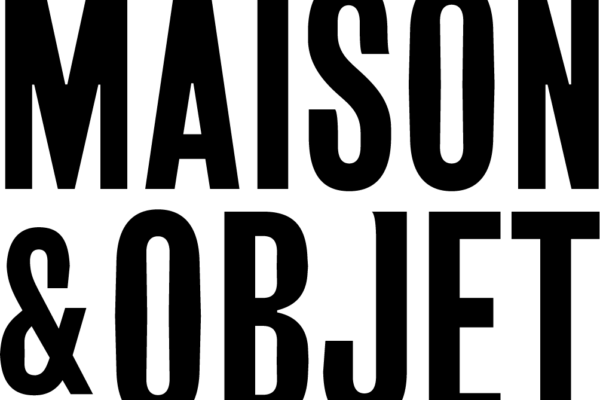少し前のことになりますが、梅雨の頃、名古屋城本丸御殿の見学ツアーに参加してきました。名古屋城と言えば天守閣の姿を想像される方が多いかもしれませんが、本丸御殿は尾張藩主の住居として徳川家康の命で1615年に建てられ、1634年には将軍を迎える上洛殿を増築、1930年には国宝に指定された建物です。ところが、戦災で1945年に焼失、天守閣は1959年に再建されましたが、本丸御殿までは復元されませんでした。それから半世紀を経た2009年、3期に分けて本丸御殿の復元工事が始まりました。2013年には、玄関・表書院の工事が完了、今年第二期となる対面所まわりが完成しました。残す上洛殿は再来年にお目見え予定です。

今回は、第二期工事のお披露目、対面所がメインとなりました。格天井の入側を進み、次の間へ。結界越しでしたが、上段之間は絢爛豪華という形容がぴたりとあてはまる煌びやかさ! 思わず目をみはりました。二重折上げ格天井は格縁が漆塗りで天井板は金箔張り。目の詰んだ柾目による造作、長押にあしらった釘隠しは格の高い六葉。床は張り付け壁、南側には付書院、北側に納戸構え。床は框も地板も桑というから驚きです。煙草盆や手文庫など小さな指物には桑を用いたものを見かけますが、幅広で長ものですから、復元にあたり材料を探し出すのに苦労があったことが伺えます。出書院も腰高障子で、腰の部分は張り付け、欄間は見事な細工の花欄間。床脇の違い棚、納戸構えも華やかな金物があしらわれていました。
対面所はもちろん、表書院、玄関も含め、すべてに精緻な技が光っていました。聞くと、愛知とその近郊県の職人たちの手になるとのこと。地域の職人の育成と技の継承にも配慮がなされていることに敬服しました。



格式高い建築の後は、わびさびの世界へ。名古屋城内の茶席を拝見しました。檜皮葺の門を潜り、大ぶりの飛び石や寄せ石敷き(時折抽象文様の刻印が施された石があって、それを見つけるのも楽しい)の露地を伝って、書院の玄関へと向かいました。十畳の座敷は、床と、違い棚と天袋を備えた床脇、付書院という床構え。床框は漆塗り、長押もまわっていますが杉面皮で、床柱も杉絞り丸太、墨蹟窓は猪目という数寄屋らしい意匠です。床脇の地板や付書院の天板などは見事な松。もともと名古屋城内に植わっていた老松で、枯れてしまったけれど永く記憶に残そうという観点で、厚板に挽いて使用されたと言います。この日は、聞香の体験もあり、床まわりにはさまざまなお香の道具によりしつらえがなされていました。(こちらは通常非公開ですが、特別公開されることもあるそうです。)



次に、書院とは渡り廊下で接続している「猿面茶席」。もとは古田織部(1543-1615年)作の茶席ですが、戦災で焼失したために1949年に復元されました。四畳半台目で下座床。この茶席の特徴は何と言っても床柱です。床柱の節がふたつ並んでいて、それが猿の顔のように見えることから「猿面茶席」と言われるようになったという説があります(ただし、復元されているので、残念ながら当初の姿は見られません……)。ここのもうひとつの特徴は窓の多さと言えるかもしれません。千利休以降の小堀遠州や古田織部の時代になると茶室の窓が多く設けられるようになったと言われますが、織部作のこの猿面茶席にも、高さの異なる連子窓、下地窓が2面の壁に穿たれています。ところが、茅葺き屋根が深く差し出されているため、陰影は深く濃くなっていて、わびた空間となっていました。



続いて、猿面茶室とは四畳半の水屋を挟んで奥にある、三畳の「望嶽茶席」。こちらは藤村庸軒(1613-99年)が造営した「澱看の席」の写しです。猿面茶席と同じ1949年に竣工しました。「澱看の席」と言えば、道安囲い(宗貞囲い)が第一の特徴として挙げられます。点前座と客座の間に中柱を立てて壁を設け、そこに火灯口を開けて太鼓襖が建てられています。この茶席では、点前の直前までは壁の向こう側で事が行われ、いざ茶を点てるに至って太鼓襖を開けるという、ドラマチックなストーリーが展開されます。壁は長スサの入った引き摺り仕上げで、床は壁も天井も塗りまわしています。本歌と同じに、落掛には華鬘釘も。



この後、織部堂や又隠写しの茶席を外観のみ見学。広大な敷地にいくつもの茶席があり、名古屋の茶道文化がいかに盛んかが伺えました。
追記:名古屋城がつくられるときには、全国からたくさんの石が集められたのでしょう。城郭の石垣、書院前の寄せ石もそうですが、手水鉢や蹲踞の石も立派なものばかりでした。書院の手水鉢は橘寺の伽藍石とも言われ、また猿面茶室前に据えた蹲踞も法華寺の伽藍石、築城のおりに運んだ車の車輪を元にした手水鉢など、とにかく存在感のある石ばかりでした。


余談:見学をひととおり終えて、お濠の脇を出口に向かって歩いているときに思わず二度見。「えっ、鹿!?」。ここに住み着いているのだとか。奈良や広島だけにあらず、鹿の生命力たるや。

(編集部 阪口公子)